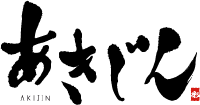赤神神社・五社堂
訪れたのは7月の下旬。
太陽がその姿を誇示するかのように輝き、蝉も長い間地面の中で貯めた力を、ここぞとばかりに大声で鳴いている。
そんな中、汗を流しながら山道を上へ上へ。その汗を拭い、疲れた足を進め続けること20分、出会えたこの五社堂。先ほどまでの苦しみはどこかに飛んでいく。
圧巻だ。999段、山道をのぼりつめて、はじめて見ることのできる風景。
ひらけたその場所に待ち構えていたように堂々とあるその社を前に、我々はただ息を飲むだけ。体が震える感動がそこにあった。
それではこれから、「そこでしか」ない、五社堂を紹介しよう。
赤神神社の拝殿の脇道から

県道59号線を北上し左手に鵜ノ崎海岸・ゴジラ岩を眺めた先、民家たちに寄り添うようにその神社は鎮座する。男鹿の潮風を浴び続けた年輪を感じされるこの建物こそが赤神神社拝殿だ。
拝殿の脇、背の低い草たちが小石を巻き込みながら黄緑色の絨毯を造る。その道の先、五社堂へと向かう石段が深い森の中に続いている。そして、森の中に入れば空気は一変する。先程まで感じていた太陽の光も、茹だる暑さも、蝉たちの騒がしい声さえも息を潜め、辺りは静寂に包まれる。聞こえるのは風に揺れる木々の音だけだ。
ふと、顔を上げれば緑のグラデーションのトンネルと石段がずーっと奥まで広がっている。幹の太い木々は自由に手を広げ、大小不揃いな岩の間から苔や植物の緑が覗く。
そうして、しばらく石段を登ればひらけた場所に出る。緑に囲まれた大きな池がのっしりと横たわり、碧色の水面に太陽の光が射し込み、池の中を覗き込めば時折、トンボが眼前を通り過ぎていく。池の隣には宝篋印塔(ほうきょういんとう)と大きな地図がある。宝篋印塔とは滅罪や延命などの利益から供養塔・墓碑塔として多く造られていたものである。

この宝篋印塔は人の身長を優に超えるほどの大きさで所々に苔が生え、石が欠け、上部分の相輪(そうりん)は別の場所に置いてある。
その隣、本山門前から五社堂近辺の古地図がある。この絵は江戸時代の初めころ、狩野派の狩野定信氏が当時の門前から西海岸地区の様子を描いた「男鹿図屏風」(県指定文化財)の写しだ。地図の中を見てみれば今はない建物があり、当時、信仰により繁栄していた様が垣間見える。
登る登る石畳み。九百九十九段。

この場で僅かながらの休憩を挟み更に上を目指す。ここから道は更に険しくなり、石段の石も大きさが揃わなくなり斜面のようになる。
険しい石段をどんどん登っていくと左手に井戸が見えてくる。これが「姿見の井戸」だ。この姿見の井戸は菅江真澄の男鹿遊覧記にも登場し、そこには「坂を遙かに登ると、姿見の井戸がある。この水鏡が曇り、真個の形が写らない人は、命が長くないと占われる。」とある。また、鈴木重孝編著本、キヌブルイには「弘法大師(平安前期の真言宗の僧であり、真言宗の開祖。)加持の御供水といい三尺余り(約90センチメートル)の丸石の井なり、深さ一丈余(約3メートル)。井水に姿を写し見えざれば、三年の中に没すという清水なり。登山の男女漱(口をすすぐこと)をなす」とある。


圧巻の五社堂現る。






ここまで来れば五社堂は目の前だ。鬼たちが積み上げた九百九十九の石段の先、男鹿の自然の中に佇む五つの社の姿は圧巻である。森に囲まれた五つの社、赤神神社五社堂である。左から、「十禅師堂」「八王子堂」「赤神権現堂(中央堂)」「客人(まろうど)権現堂」「三の宮堂」と呼ばれ、赤神神社に伝わる九百九十九の石段に登場する五匹の鬼たちを祀っていると言う。また、建保四年(1216)に比叡山の山王七社を勧請して造られたが、その後二社が廃れたため現在の五社になったとも言われる。橘氏、安東氏の崇敬を受け、国替えにより秋田へ移った佐竹氏に篤く信仰された。
現在の五社堂は宝永七年(1710)に建てられた。また、赤神権現堂内にある厨子(ずし。仏像・教典・位牌などを中に安置する仏具の一種)は、室町時代後期のものと推定される。
これら五社堂と、赤神権現堂内の厨子は国により重要文化財に指定されている。
五社堂は正面入母屋造と言われる平安時代より神社で応用された様式で、形は同じだが、よく見ると細かな装飾などはひとつひとつ異なっている。イノシシや象などが彫られた柱をじっくり観察してみてはどうだろうか。
五社堂の右側にはお守りなどが売られており、その奥には伝説の中に登場する逆さ杉が置いてある。また、休憩用の椅子が数個置いてあるので、自然の音を聞きながらゆっくり休憩するのも良いだろう。
人々の喧騒から遠ざかり、ふきと県の木である杉、山の静寂と生き物たちのさざめきに囲まれながら赤神神社はこの場所に在り続ける。
文/石塚
赤神神社伝説
黒神と赤神のたたかい。

昔々、津軽の竜飛というところに黒神という神様と南部の十和田湖には一人の美しい女神がいました。また、出羽の男鹿にも赤神という神様がいました。
女神の姿は美しく、彼女の着物の裾は百鬼四方に美しく輝いたと言います。ところがその女神を我のものにしようと考える黒神と赤神のどちらからも言い寄られ、女神は困り果ててしまいました。
女神は赤神の情け深く優しい気持ちに一旦惹かれましたが、顔が鉄のように光り元気が良く、勇ましい働きぶりをする黒神にも惹かれましたので、決めかねていました。
昨日は黒神が竜に乗って女神を訪ね、身に沁みるような心温まる気持ちを伝えられました。また、今日は赤神の鹿の使いが来て赤神の気持ちを書いた手紙を持って言い寄られました。ですが、女神は黒神の話を聞いたり、赤神がしたためた手紙を読んだりする内に、どうしていいか分からなくなってしまいました。そして、遂には手紙の上に崩れほろほろと声を上げて泣いてしまいました。
黒神は自分の競争相手に赤神がいることに気付きました。また赤神も自分より先に女神に近付いている黒神がいることを知りました。二人の間で争いが起きるようになり、そしていつしか激しい戦いになってしまいました。お互いに何回も何回も攻め合いましたが、勝負はつきませんでした。
その時、八百万の神たちは津軽の岩木山に集まって二人の激しい戦いを見物していました。そして、黒神が勝つという方は右へ赤神が勝つという方は左へと見物の神々も二つに分かれてしまいました。この時黒神が勝つという方が多く、山が神々に踏み崩されてしまったので、岩木山の右側が低くなってしまったそうです。
赤神の方にも立派な武者がいましたが、太陽が空から海に落ちるという幻を見ていなくなってしまい、赤神の勢いはどんどん衰えてしまいました。そのため黒神は男鹿の根城まで来ました。
黒神に追い詰められた赤神は刀が折れ矢もついて、「空寂」という穴に隠れて、二度と出てこないと誓ったそうです。それを聞いた黒神は、さらばと言って帰ってしまいました。
黒神は勝ったというめでたい知らせを女神に知らせようと刀に付いた血糊を拭いもせず、十和田湖に向かいました。ところが女神の姿はそこにはありませんでした。女神は戦いに負けた赤神に同情し、「空寂」の穴に移っていたのでした。
それを知った黒神は天を仰いで百千年の息を一度に吐いてがっかりしました。この時吐いた息で今の北海道は津軽から離れたと言われています。
今でも津軽の竜飛に行くと、岩がみな黒く打ち寄せる波も荒いです。ちょうど黒神のような雄々しい神様の住処であったように思えます。また、男鹿の岩は多くが赤味を帯びています。大桟橋(だいさんきょう)、小桟橋(しょうさんきょう)などには他には見られない鬼の住んだあともありますが、どちらかというと岩は穏やかな形をしています。
空寂の窟は、今は蒿雀窟、孔雀窟という名前で残っています。窟の深い深い奥底には一つの石の扉があって、その扉を開くと雪のように白い女が立っているという話もあります。そして戦いに倒れた赤神の家来は、男鹿市北浦の山野一面に咲く曼珠沙華(彼岸花)だと言い伝えられています。
赤神神社伝説
九百九十九の石段


昔々、漢という国に武帝という人がいました。ある時、その武帝が白い鹿の引く飛車に乗り、5匹のコウモリを従えて男鹿にやってきました。コウモリたちはいつしか5匹の鬼へと変化しました。そして武帝は毎日のように鬼たちを働かせていました。
ある日、5匹の鬼たちはあつまって
「どうか、一日だけでいいから、俺たちに休みをくれ」と武帝に頼みました。
武帝は鬼たちが普段からよく働いているので
「それならば、正月の15日は一日だけ休みを与えよう」と言いました。
すると自由を得た鬼たちは大喜びで里に降り、家畜や作物を奪うのを繰り返し、ついには里の娘を攫っていくようになりました。そこで怒ったのが村人たちです。彼らは鬼を退治しようと決心して、ある夜、武器を手に鬼退治に行きました。
ところが、力の強い鬼たちに返り討ちに合ってしまいました。
困った村人たちは武帝にお願いし鬼たちに
「五社堂まで続く千段の石段を一晩で、しかも一番鶏の鳴く前に築くことが出来たら、娘を毎年一人ずつ差し出そう。もし出来なければ二度と里には降りてこないでほしい」という賭けを持ちかけました。
村人たちはいかに鬼たちが怪力であっても一晩のうちに、千段の石段を作れないだろうと思っていたのです。
一方その頃、鬼たちは日が暮れるのを待って石段作りにとりかかりました。鬼たちは大きな岩石を抱え、あれよ、あれよと、石段を積み上げていきます。このままでは一番鶏が鳴く前に出来上がってしまうと慌てた村人たちは、物真似の上手いアマノジャクに鶏の鳴き真似を頼みました。
鬼たちが九百九十九段まで積み上げ、あと一段のところでアマノジャクの
「コケコッコウ」という声が聞こえました。
鬼たちは飛び上がって驚きました。やがて、驚きは怒りに変わり、ぶるぶると体を震わせ、髪を振り乱し雷のような恐ろしい声を上げました。そして、傍に生えていた千年杉の大樹をむんずと掴み、木の根を上にして大地にぐさりと突き刺しました。鬼たちはさっさと山に帰ってしまい、それから再び村に降りてくることはありませんでした。
その逆さ杉は根を空に向けて生えていましたが、今は枯れてしまい横になった状態で保存されています。
門前にある赤神神社から五社堂までの石段は今も続いています。五社堂はこの5匹の鬼たちを祀り、昔を物語っています。これが今日のナマハゲのおこりとも言われています。
寄稿者から
日常から離れ、神聖な雰囲気を味わうことができる男鹿の赤神神社・五社堂。現実を忘れて癒されるのに最適な場所だと思います。ぜひ訪れてみてください。
Information
赤神神社・五社堂

一気に石段を駆け上がるのもいいが、周りの風景を楽しみながら登れば更に男鹿の自然を楽しめるでしょう。五社堂周辺は綺麗に整備され、ゆっくり五社堂を眺めながら休憩もできます。参道から見て右側にお守りなどを売っている社務所もありますので、ここで赤神神社参拝記念に自分やお土産用のお守りを買うと良いでしょう。また、おみくじもありますので、旅の運試しにどうぞ。
雨天時、または冬季期間中に登るのは危険ですのでお気を付けください。
〒010-0535 秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川35 赤神神社五社堂
男鹿駅から車で20分。駐車場有り。
赤神神社から五社堂までは、山道を20~30分ほど登る。